それぞれの価値創造を語る
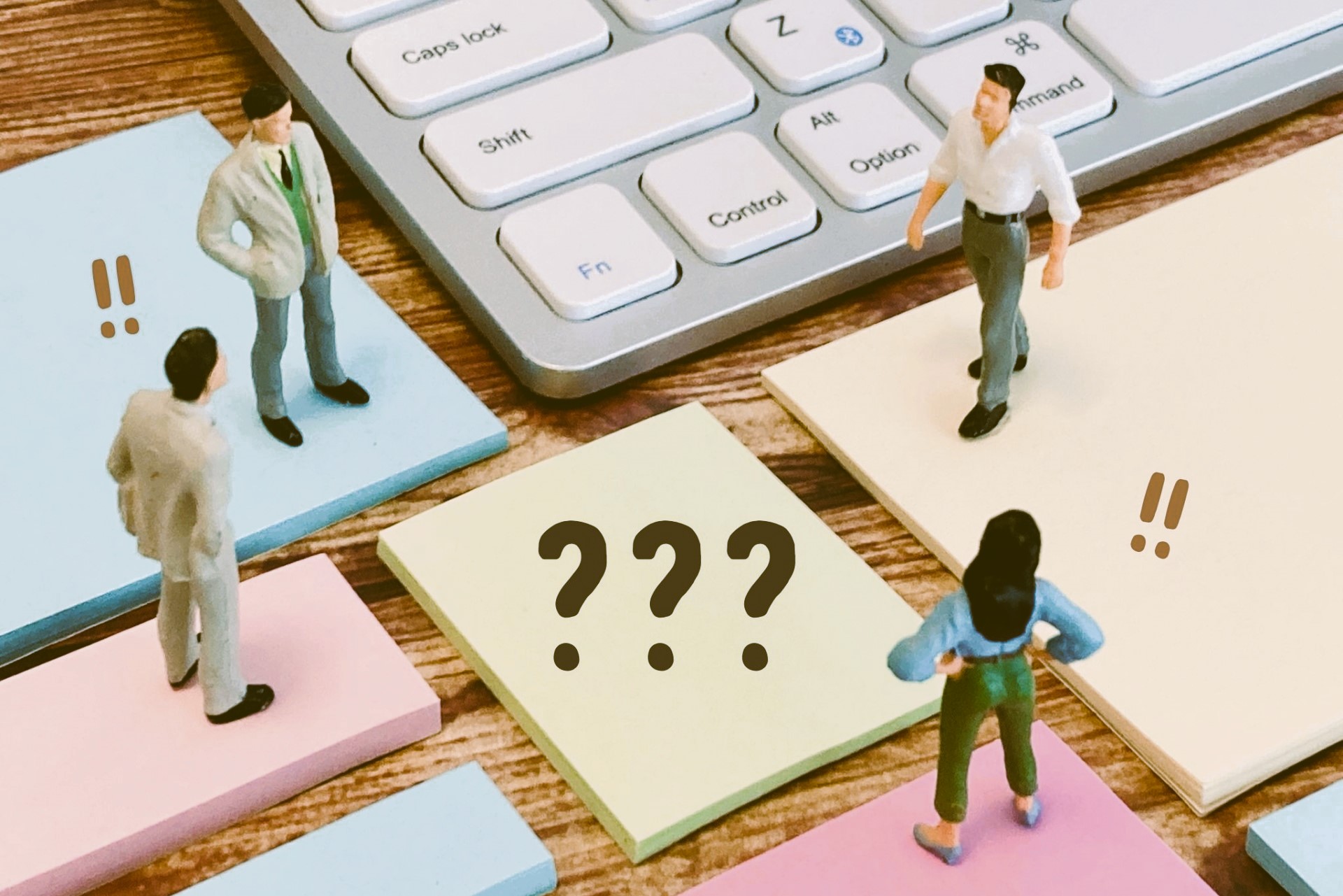
「価値」。私たちは、日常的に物事の「価値」について評価をしながら生活しており、一人ひとり、それぞれが評価基準を持っています。自分自身を見つめれば、その基準に意識的なものと無意識なものがあることに気付くはずですし、他者に目を向けると、趣味嗜好、生活習慣、仕事ぶりからその評価基準を覗きみることもありますが、なかなか理解が難しいものです。さらに、私たち建設コンサルタントが日々向き合っている「社会にとっての価値」まで視野を広げると、その概念や本質を捉えることは、本当に難しくなります。
今回のテーマは「価値創造」。この手強いテーマと向き合うにあたり、CFKの35歳以下社員を対象にこだわりや価値観についてヒアリングし、その声をたどりながら執筆メンバーで座談会を実施しました。それぞれの考えや価値観、目指す姿について語り合いました。
座談会参加者
山本 優里 計画系部門 地域整備グループ
菊地 佑 道路系部門 道路第一グループ
干野 一騎 鉄道系部門 地下鉄道グループ
藤田 和輝 構造系部門 トンネルグループ
執筆
加藤 慎吾 構造系部門 橋梁・長寿命化グループ
人と人のつながり
菊地:35歳以下の社員へのヒアリングをみると、それぞれのこだわりや価値観の背景に、出身や学生時代の経験といった様なそれぞれのルーツがあることが見えました。それを価値創造の観点でとらえると、その人そのものが仕事のディティールに現れて、技術者の色や味になるのだと感じます。日常生活で使うお醤油やお米の好みの話題もありましたが、そういうこだわりが仕事のこだわりにグラデーションで変わっていく。そんな人と人とのコミュニケーションが、価値創造につながっているような気がします。
山本:社内の友人と同じ趣味を楽しんだり、飲みに行ったり。業務で一緒に仕事をするだけではなくて、ルーツとか趣味を知ったうえで仕事で関わると、それぞれの考え方や価値観が現れやすくなって、新たな発見につながりますよね。中途入社の私にとっては、今回の若手ヒアリングだったり、別の社内活動でも色々な人と出会えているのは、仕事をする上での助けになっています(詳しくは特集記事参照)。

特集「価値創造」
特集記事:様々な経験や想いを紡ぐことで生まれるもの
そんな人とのつながりの中で、精神的な安心感のある、自分の意見をちゃんと伝えても受け入れてもらえる環境があることも大切です。私自身、後輩や上司との関係づくりで気にかけています。意見が違っても、否定ではなくて前向きに捉えて意見を出しやすい環境。そういう場で、価値創造が起こると思います。
行動を生む原動力

山本:ヒアリングでは他にも、気になる場所には実際に足を運んで体験する、好き嫌いせずやってみる、という声もありました。言葉の発信と同じように、やりたい気持ちを行動で実現できる環境も、大切だと思います。
干野:好奇心、伝えたい気持ち。そんなエネルギーがポイントですよね。プライベートだと、自分の部屋を好きなもので一杯にしたり、そんな行動の根幹にあるエネルギー。新しいものを生みだし、それを提案して形にしていくことにおいて大事なものではないでしょうか。
価値観と知識の継承

干野:いまの私の場合、仕事でエネルギーを向けている矛先は、業務の結果をとりまとめる報告書づくりです。読む人に検討の思想や過程がキチンと伝わるようにこだわっています。情報が残っていないせいで、既に検討されたことを後の人が繰り返し検討するようなことが起こると勿体ないですよね。実は以前、上司が作成した昔の報告書を見ることがあったのですが、検討内容がとても細かく残されていて、業務に取り組むうえでもすごく助かったんです。だから私も、読む人に検討の思想や過程がキチンと伝わるようにしたい。教わるというよりは、具体例を見ながら受け継いだ価値観だと思います(詳しくは特集記事参照)。

特集「価値創造」
特集記事:「鉄道の人」を受け継ぐ」
力を合わせて
藤田:報告書や図面に示すべき情報が何であるか。これを理解するには、失敗も含めて、経験を重ねて学ぶ部分が大きいです。私たちにとって、経験を補ってくれる情報は、本当に助かります。
そういう情報や知識の蓄積に関しては、広い分野に対応した技術者に憧れや必要性を感じることがあります。例えば、道路、トンネル、橋梁は、技術分野としては別ですが、それぞれの専門知識を一人の技術者が持っているような姿です。しかし、ひとりの技術者に出来ることには、限界があります。それなら3人でやった方がいい。同じ知識をベースにしていても、違う人間がそれぞれ違う角度で見て、考えることができます。そこから生まれるアイデアを重ねることで、より良いものを生みだせると思うのです。複数の部署で協働したプロジェクトだからこそ、生みだせた成果があります(詳しくは特集記事参照)。

特集「価値創造」
特集記事:「幅広く柔軟な思考」
菊地:ベテランでも若手でも、一人の技術者が生み出すものにはどこか抜けができますよね。若手だと知識不足だったり、ベテランだとこだわりが裏目に出たり。そういった意味で、いろんな人から意見を貰うのは大事だと感じています。それは年齢でこだわるものでもなく、ある業務では、特に若手メンバーで議論を重ね、力を合わせて取り組んだ結果、一人ずつでは出し得ない力を発揮することができました(詳しくは特集記事参照)。

特集「価値創造」
特集記事:繋がりが繋がりを生む
“今”を超えて変化する

山本:以前、都営地下鉄のホームドア整備の車両改修コストを約20億円から約270万円へと大幅削減したニュースをみたのですが、ご存知ですか?車両位置検知のシステムにQRコードを用いるアイデアで実現されたそうですが、その発案は技術系職員によるものでした。アイデアを発信し、それが聞き入れられる環境であれば、メンバーが力を合わせることでこんなにも大きな成果が生まれる。
干野:私も鉄道設計に携わる技術者として、将来の計画路線の線形を引くということもやってみたいと思っています。きっとその実現には新しい技術が必要で、既往の知識を超えたアイデアが必要になるでしょう。今の技術ではかなえられないものを実現する、面白い提案のできる技術者になりたいですね。
藤田:そんな幅広な技術者像や仕事ぶりを目指すとすると、今の部署にいながらでも、他部署領域の仕事からも学びが必要ですよね。そして、常に柔軟でいないといけない。
菊地:社内にとどまらない、社外との繋がりも大切ですよね。私自身についていえば、オフィス環境リニューアルやドイツへのインフラ視察で社内外の人と通常業務以外で関わることが増えました。様々な考え方に触れ、自分自身の価値観に変化が生まれてきました。そういったことの積み重ねが、新たな価値創造につながるように思います。
おわりに
座談会を通して、4人それぞれの価値観について共有することができました。異なる個性を互いに理解し、そして影響を与え合うこと。それが、価値創造につながっていくでしょう。
