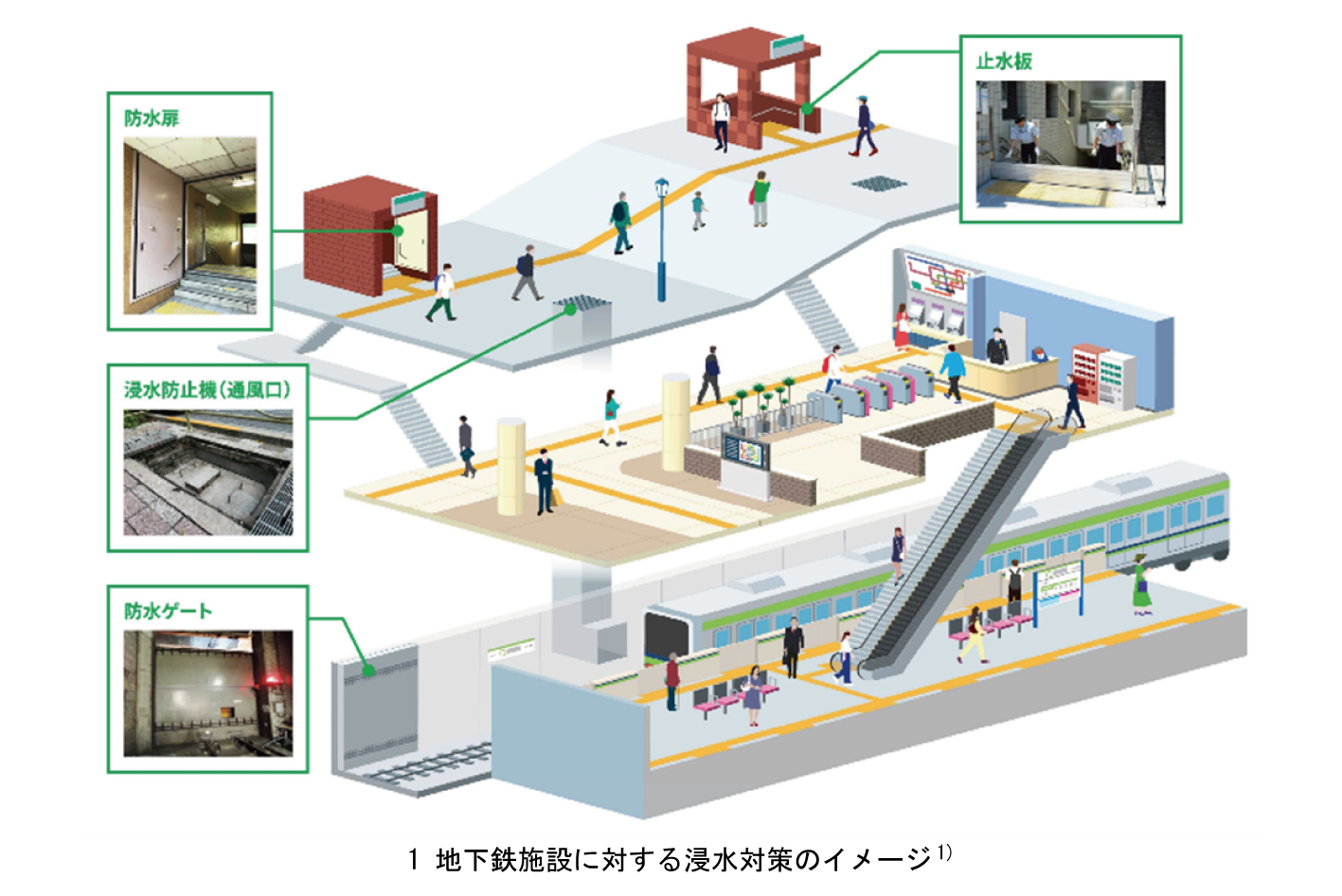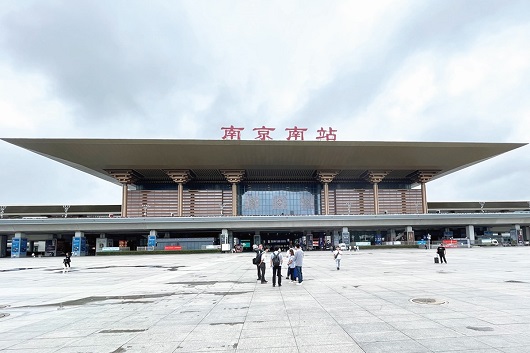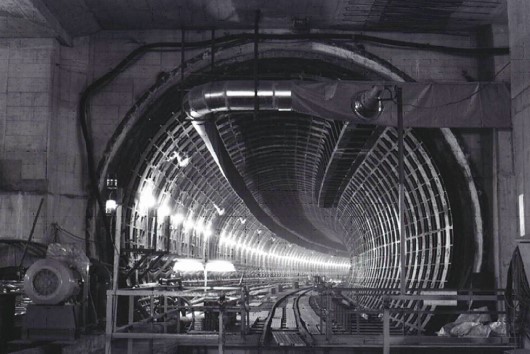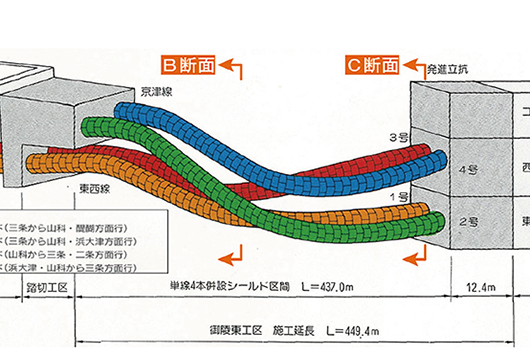鉄道の人
「価値創造」について考えるにあたり、先日ふと他部署の社員に言われた「鉄道の人は『鉄道の人』って感じがするよね」という言葉を受けて、私が所属する鉄道系の部署にて代々受け継がれる何かがあり、それが持つ価値があるのではと考えてみました。
客先との関係性
上司に「鉄道特有だと感じることはあるか」と尋ねて、真っ先に返ってきた答えが『客先との関係性』でした。いわゆる役所では、数年で異動があるので、毎回異なる個人が客先となります。一方、鉄道事業者は少し特殊で、民間はもちろん、役所であっても一個人と長く、深い付き合いになることが多いです。1年目の頃に、とある事業者との打合せに初めて参加したときには、いかにも旧知の仲といった様子で雑談を交えつつ、腹を割った議論が行われている光景に驚いたことを記憶しています。
このような信頼関係が背景にあることで、客先のツボ(特に知りたい、気になる要点)を押さえ、新たな知見を提示できるというのは、客先にとってCFKが持つ大きな価値の1つなのではないかと感じます。同時に、信頼を得ることで、継続して事業に携わることが出来るのは、企業としても技術者としても大切なことです。
受け継がれる知識・経験・考え方
CFKには、携わった設計は数知れない、業界最前線で基準の制定にも関与してきた百戦錬磨の諸先輩方が沢山います。そして先輩らは、「ここはこうしておくもんでしょ」といったいわゆる感覚論のようなことをよく言います。最初はなかなかそれが理解できませんが、経験を積む中でそれらを紐解けるようになっていくと、施工性への配慮や、過去に経験した事象に対する余裕代といった、経験に基づく合理性の積み重ねであったりすることが解ってきます。こういった感覚は大先輩らから受け継がれてきたCFKの設計が持つ大きな価値の1つであり、日々、我々が「わかっとらん」と指導される先に習得を求められているものなのかなと思っています。
基準をただ守るだけではだめ?
またも1年目の話でありますが、海外に日本の技術で地下鉄を造るプロジェクトで、新駅の設計に携わりました。その中で、大ベテラン社員の構造計画を読み解くという機会がありました。考えを読み解いていく中で、階段上方の内空高さ(※地下鉄の階段は、頭をぶつけないように一定以上の空間を確保できるよう設計する)が、日本の基準にある最小値よりも大きめに確保されていることに気が付きました。小さい方が構造的、施設配置的に有利なので、わざわざ大きくした理由を尋ねてみたところ、「海外の駅なので背が高い人が多いだろうから、大きめの内空にしてみた」と返事が返ってきました。結果的には最小値に修正することになったのですが、この何気ない提案は、ただ基準を順守してコストや効率を追求するのみの発想では生まれない、利用者への配慮によるものであり、1つのあるべきコンサルタント像として強く印象に残っています。
「中央復建」に要求されるもの
これまで、自身の経験を振り返りながらいろいろと述べてきた中で、以前客先に「中央復建ならこれくらいできなくてどうする」と言われたことを思い出しました。今思うと、この言葉は先輩らが客先と信頼を築く過程で、高い価値を示し、中央復建に求めるハードルを引き上げてきた証といえるのかなと感じます。自分も後進へ高いハードル(期待)と信頼を引き継いでいけるよう精進します。

干野 一騎HOSHINO Kazukii
鉄道系部門
地下鉄道グループ